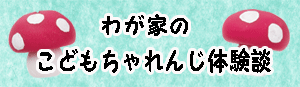(2018年5月27日更新)
【お知らせ】「コトコトとやま」のFacebookページができました。
最新の更新情報や、おすすめのおでかけ先が知りたい方はフォローをお願いします(^^)! → https://www.facebook.com/KEIKOTOKOTO/
こんにちは。富山県で5歳男児子育て中のアラフォー主婦KEIです。
このブログは、子どもとの日々のお出かけ先に悩むママたちに向けて書いています。
児童館って、小学生が放課後や休日に行くところでしょ?
乳幼児には、関係ないよね~!
そんな風に思っているママ、いらっしゃいませんか?
いえ、そう思い込んでいたのは私なんですが・・・(-。-;)。
私が初めて子連れで受動館に行ったのは、ママ友に誘われて訪れたのがはじめだったと思います。
いざ行ってみると、「子育て支援センター」並みに匹敵する乳幼児専用の部屋があることにビックリでした。
【関連ページ】「子育て支援センター」8カ所紹介
児童館の乳幼児室と「子育て支援センター」はかなり似ているのですが、「児童館」にはまた違った個性があります。
この記事では、児童館の設備や特徴、私が行った7つの児童館について紹介しますね(^^)!
そもそも児童館ってどういう施設なの?
児童館の役割
そういえば児童館って昔からあるけど、どんな施設で、誰を対象としているのでしょうか?

あまり考えたことがなかったので、少し調べてみました。
「厚生労働省」のサイトに、「児童館について」というページがありました。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/jidoukan.html
———-以下引用———-
【児童館概要】
「児童館」とは、健全な遊びを通して、子どもの生活の安定と子どもの能力の発達を援助していく拠点施設です。
【対象となる児童】
18歳未満のすべての児童。
【児童館の事業】
児童の健全な遊び場の確保、健康増進、情操を高めることを目的とした事業
——————–
・・・これらを、勝手にまとめると、
「18歳以下なら誰でも利用できる遊び場。
子供の心身の発達に貢献する施設だよ!」
ってとこでしょうか。
そんなわけで、どうも0歳から利用していいようです(^^)!
大きい子の邪魔になったら嫌だなと思っていましたが、遠慮なく乳幼児を連れて遊びに行きましょう!
児童館の設備
児童館の規模によって、施設の種類はいろいろです。
簡単に、主要な部屋を紹介しますね。
乳幼児室
小学生以下の子供が利用する部屋。

乳幼児が好むおもちゃや、ベビーベッドが置かれています。
畳敷きになっている場所もあり、赤ちゃんでも安心して遊ばせられます。
遊戯室
体育館のような広いホール。

ボール遊びや、フラフープ、一輪車、卓球などなど、自由に体を動かして遊ぶことができます。
場所によっては、トランポリンなど大型遊具が常設されているところがあります。
図書室
子供向けの本が置いてあり、落ち着いて読むことができます。
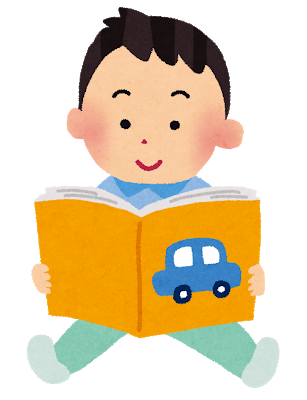
絵本や紙芝居が置いてあるところもあります。
学習室(児童室)
小学生が学習する部屋です。
乳幼児は、立ち入り禁止な場合が多いです。
工作室
製作活動をする部屋です。

他にも、調理室や集会場、学童保育用の部屋、パソコンルームなど、場所によって様々です。
児童館の特徴と注意点
こちらでは、児童館の特徴と利用の際の注意点を書いておきます。
(1)幅広い年齢層の子と遊ばせることができる
児童館の魅力は、子供を幅広い年齢の子と遊ばせることができる点です。
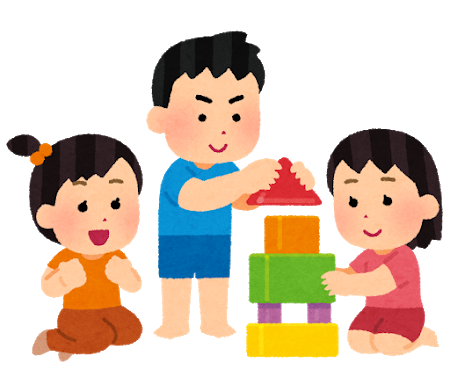
同年代はもちろん、少し年上の子や、生後数か月の赤ちゃんと出会うこともできます。
おもちゃの取り合いや、滑り台の順番待ちなどケンカになることもありますが、子供が社会性を身に着ける貴重な経験をすることができます。
(2)乳幼児向けサークルがある
事前登録制の、サークル活動が行われています。
年齢別に分けられていることが多く、中には人気のあまり抽選になるところもあります。
一方、その児童館のサークルに入っていない場合、サークルで使用している間、その設備が使用できません。
以前サークル活動をやっている日に行ってしまい、遊戯室が使えず子供が暴れて大変な目にあったことがあります(>-<)。
「せっかく遊びに来たのに、限られたスペースでしか遊べなかった」ということが起こります。
可能であれば、児童館のイベントページをあらかじめチェックしておくといいですね。
(3)自由にさせてくれる
よほどお願いしない限り、児童館の先生は「自由に遊んでいってね」というスタンス。

「子育ての悩みをじっくり聞いてほしい!」という人に児童館は、物足りないかもしれません。
育児相談のあるお悩みママは、「子育て支援センター」に行きましょう。
むしろ勝手に遊ばせてほしいというママには、最適の施設だと思います(^^)。
(4)赤ちゃんのお世話設備が、手薄なところもある
児童館によっては、授乳室がない施設があります。
あっても、カーテンで軽く仕切るだけの簡単な設備だったり・・・。
最近はイクメンパパも多いし、ちょっと落ち着かないかもしれません。
オムツ替えベッドも、廊下にポンと小さいベビーベッドが置いてあるだけ、という場所もあります。
贅沢はいえませんが、「子育て支援センター」に比べると、少し手薄さを感じることがあります。
(5)水分補給はOK。食べ物は不可。
水分補給は、指定の場所ですることができます。
食べ物を食べるのは禁止されています。
(6)大きい子との関係が難しい
児童館の利用者は、0歳~18歳と非常に幅広いです。
体が大きくて元気な子と遊戯室で一緒になったら、小さい子に衝突の危険があります。
また「私たちが遊んぶのだから、邪魔しないで」とはっきり言ってくる小学生もいましたw。
実を言うと、私が児童館を利用するのは、平日午前中が多いです。
子供を安全に遊ばせたいママは、大きい子の来る時間帯を避けるのもいいと思いますよ。
(7)遊戯室に空調がない
児童館の各部屋は空調が整っているのですが、広い遊戯室は何も入っていないことが多いです。
夏は暑く、冬は寒い(^^;)。
特に冬の遊戯室は靴下を履いていても、床の冷たさが伝わってしもやけになりそう。
冬場の遊戯室には、内履きを持っていくことをおすすめします。

児童館9ヶ所紹介
それでは、私が行った児童館9カ所を特徴とともに紹介したいと思います。
気になる場所があったら、リンク先のページを読んでみてくださいね。
【射水市】こどもみらい館
言わずと知れた、ダントツで人気の富山県立児童館。
館内に張り巡らされた立体アスレチックに、いつでも工作に挑戦できる複数の工作室、イベントも多数行われる魅力的な空間です。
建物にたどり着くまで時間がかかるのが唯一の難点。
【氷見市】氷見市児童館
同じ建物内に屋内巨大アスレチックがある、元気な子にはたまらない児童館。
天気の悪い日でも思いっきり体を動かせるのが嬉しい。
館内に「子育て支援センター」もあるので、赤ちゃん連れにも嬉しい施設です。
【富山市】水橋児童館
昭和の雰囲気漂う、アットホームな児童館です。
建物が古くとも、遊具やオモチャは新しいし、遊戯室もちょうどいい広さ。
館庭には、楽しい遊具が揃っています。
遊戯室にトランポリンが常設されているのが嬉しい。
【富山市】北部児童館&馬場記念公園
2017年3月にリニューアルした、ピカピカの児童館です。
【馬場記念公園】の中にあり、建物の外には公園の遊具や芝生広場が広がっています。
児童館の中も、広い公園の遊具も一度に楽しめるのが魅力。
駐車が難しいのが残念な所。
【富山市】五福児童館
冬になると、床暖房がつく嬉しい施設。
もちろん夏場は冷房がついていて快適です。
いつもほどほどの来館者数で、「ものすごい混んで困った」ということはありません。
とても居心地がよく、子供と通いたくなる児童館です
【富山市】東部児童館
新しくて広くて冷暖房完備の、ステキ児童館。
最大の魅力は、遊戯室に多彩な遊具が常設で置いてあるところ。
元気っ子におすすめ!
人気施設のため、土日や雨の日はこみ合うこともあります。
【滑川市】滑川市児童館
2016年の春にリニューアルオープンしたピカピカの児童館。
赤ちゃんとママがのんびり過ごせる乳幼児室から、小学生が体操できるアスレチックまで、幅広い年齢層の子供が楽しむことができます。
遊戯室の1階から2階にかけて張り巡らされたアスレチックは、圧巻の一言です。
【富山市】婦中児童館&子育て支援センター
のんびり室内遊びもしたいし、広い遊戯室で走り回りたい、そんな両方の希望を叶える児童館。
多くの児童館は9:30開館が多いのですが、婦中児童館は土曜・春夏冬休みの期間中、早朝8:30から開館。
早朝から外出をせがむ子供を連れて行くことができます。
【富山市】山室児童館
小規模ながらも、魅力的なオモチャや遊具を備えた、アットホームな児童館。
あまりこみ合わず、のんびりと過ごすことができます。
乳幼児室には、魅力的な滑り台や、つり橋の遊具が備えられていました。
新しくはありませんが、落ち着いた雰囲気の施設です。
富山の「児童館特集!」まとめ
児童館の役割や注意点、私が行った7カ所の児童館についてまとめました。
実をいうと、児童館を特にお勧めしたいのは・・・
「家の外に出て息抜きしたいけど、あんまり人にかまわれたくない」というママ(-▽-)。
基本的に児童館の職員さんは「自由に遊んでいってね」というスタンスです。
「子育て支援センター」に比べると、「ママ同士仲良くなりましょうね!」という無言の圧力も少ないように感じます。
ぜひ私のようなコミュ障ママは児童館に行ってみて下さいね!
子どもと児童館へのお出かけを楽しんだら、おうち時間も充実させませんか?
>>わが家がお世話になっている「こどもちゃれんじ」体験談はこちら!